図は、口を大きく開けた時の中の様子です。口の中は舌・口腔底(舌と歯ぐきの間の溝)・上下の歯肉(歯ぐき)、口蓋(上あご)・頬粘膜(ほほ)、口唇(くちびる)などがあり、そこにできたがんをまとめて口腔がんと言います。その中で最も多いのは舌がんで約半数を占めています。日本人ではがん全体の2%程度で、年間の患者数は8000人前後ですが年々増加傾向にあります。高齢者ほど発症しやすく、約8割は50歳以上です。
特に初期のうちは痛みなどの症状が少ないので、がんだとは思わない患者さんも多く、そのため口腔がんの約8割は進行した状態で発見されます。早期発見できれば5年後の生存率は90%以上ですが、進行がんでは約50%に低下し、治療後も大きな機能障害が残ってしまいます。
初期症状は痛みや粘膜のただれで、口内炎と似ているので気をつけてください。通常の口内炎は1週間から10 日ほどで治りますが、がんは自然には良くなりません。口内炎が2~3週間以上たっても治らず、痛みやただれが強くなり腫れてくるようなときは迷わずに耳鼻咽喉科や頭頸部外科、あるいは口腔外科を受診してください。
さらに血の混じった唾液が出てきます。虫歯や歯槽膿漏と区別が付きにくい時は歯科でチェックしてもらって下さい。
また、口腔がんの約3割の人では、がんの発見時にすでに首のリンパ節に転移しており、首のグリグリとして触ることができます。
通常の健康診断では見つかりにくいので、早期発見には自己検診が大切です。
まずは手鏡を使って口の中をよく見てください。白いまだらな部分があれば前がん病変(がんの前触れ)の白板症かもしれませんので要注意です。さらに舌や口の中の粘膜をさわってみて、硬くなっている・ざらざらしている・でこぼこと腫れているといったところがあったり、指先に血が付いてくることがある場合も要注意です。
①治りにくい口内炎に注意
舌の痛みやしみる感じが2-3週たってもよくならない時は要注意
②おかしければ舌を自分でさわること
表面のざらざらや硬いしこりを感ずる場合やこすって血が付き時も要注意
③舌の白い斑点は前癌病変かもしれない
表面の変化(でこぼこ、潰瘍など)にいつも注意する
舌です。口腔がんの約50%を占めます。特に歯と絶えず接触する舌の側面にできることが多く、部分的に硬く盛り上がったり、潰瘍を作ったりさらに白く変色したりしていれば、がんの疑いがあります。すぐに医師に相談してください。次いで多いのは舌と歯茎の間のくぼみの「口腔底」という部位です。
口腔がんを起こしやすいリスクがある程度分かってます。それらを避けることが重要です。
1.歯による刺激:口腔内の粘膜が歯の刺激で絶えず傷ついていると、がん化しやすくなります。部分的に欠けてとがった歯があったり、噛み合わせや歯並びが悪い、入れ歯が合っていないなどは要注意です。その様な場合は、是非歯科で調整してもらってください。虫歯など口の中の不衛生も良くありません。
2.喫煙:たばこの嗜好者は口腔がんになりやすいことが分かっています。日本で男性の患者数は女性の患者数の約2倍に達しているのはそのためかも知れません。
| TX | 原発腫瘍の評価が不可能 | |
|---|---|---|
| T0 | 原発腫瘍を認めない | |
| Tis | 上皮内癌 | |
| T1 | 最大径が2cm以下の腫瘍 | |
| T2 | 最大径が2cmを超えるが4cm以下の腫瘍 | |
| T3 | 最大径が4cmを超える腫瘍 | |
| T4a | 骨髄質、舌深層の筋肉(外舌筋)、上顎洞、顔面の皮膚に浸潤した腫瘍 | |
| T4b | 咀嚼筋間隙、翼状突起または頭蓋底に浸潤した腫瘍、または内頸動脈を全周性に取り囲む腫瘍 | |
| NX | 所属リンパ節転移の評価が不可能 | |
|---|---|---|
| N0 | 所属リンパ節転移なし | |
| N1 | 同側の単発性リンパ転移で最大径が3cm以下 | |
| N2a | 同側の単発性リンパ節転移で最大径が3cmを超えるが6cm以下 | |
| N2b | 同側の多発性リンパ節転移で最大径が6cm以下 | |
| N2c | 両側あるいは対側のリンパ節転移で最大径が6cm以下 | |
| N3 | 最大径が6cmを超えるリンパ節転移 | |
| MX | 遠隔転移の評価が不可能 | |
|---|---|---|
| M0 | 遠隔転移なし | |
| M1 | 遠隔転移あり | |
口腔癌は問診、視診、触診などの診査で通して腫瘍の進行状態をある程度把握し、次に画像検査、組織検査(生検)を行うことが多い。
腫瘍の進行状態を規定する因子は、腫瘍の大きさ(T)、頸部リンパ節転移(N)、遠隔転移(M)である。これらは治療法の選択に際して重要で、生命の予後に多大な影響を及ぼす。判定にあたってはTNM 分類(表3-1)や病期分類(表3-2)、口腔癌や頭頸部癌取扱い規約が採用されている。原発巣に関しては、(1)発生部位、(2)臨床発育様式、(3)腫瘍の厚み、(4)周囲組織への進展程度などが、原発巣再発や頸部リンパ節転移、遠隔転移と関連するといわれている。
頸部リンパ節転移については、転移レベルが進行するほど、転移個数が増えるほど、周囲組織との癒着が認められるほど、頸部再発の頻度や遠隔臓器への転移傾向が強くなるとの報告がある。初診時の触診による慎重な診査が大切であるが、確定診断にあたっては触診に加えて、さらに画像検査が必要である。
さまざまな臨床症状(神経麻痺、疼痛、構音障害、嚥下障害、開口障害、体重減少など)が、腫瘍の病態や進行状態と関連しているといわれている。
原発巣の治療(舌癌、口底癌、頬粘がん、下顎歯肉癌、上顎歯肉癌、硬口蓋癌)頸部転移巣の治療(頸部リンパ節のレベル分類、頸部郭清術の基本術式、頸部郭清術式の適用、頸部郭清術の補助療法)術前・術後の補助療法再発癌の治療緩和医療
口腔癌は、舌、口底、頬粘膜、上顎歯肉、下顎歯肉、硬口蓋など解剖学的構造の異なった部位に発生するために、癌の病態や進展様式は各部位によって大きく異なる。そのため治療法も各部位によって異なってくる。口腔癌の外科切除では、咀嚼および摂食・嚥下、発音などの機能面ならびに顎顔面領域の整容面に及ぼす影響も大きいため、術後の患者のQOLを重視した治療体系が望まれ、欠損部については再建や、上顎では顎補綴も考慮した外科療法を行う必要がある。
ここでは、口腔癌のなかでも発生率の高い舌癌ならびに下顎歯肉癌を中心に、各部位における外科療法ならびに気管切開について解説する
舌癌は原発巣の大きさ、浸潤の深さおよび周囲組織への進展により切除範囲が異なる。具体的には、口底浸潤、舌根浸潤、下顎骨浸潤の有無、程度による。原発巣の切除範囲が大きければ、皮弁または筋皮弁による再建手術が必要となる。 舌癌T1N0、 earlyT2N0 症例、表在性のlateT2N0、 T3N0 症例は口内法による舌部分切除を行う。lateT2N0、 T3N0、 T4N0 症例は原発巣切除(舌部分切除、舌半側切除、舌亜全摘出など)とともに予防的頸部郭清を行うため、pull-through 法にて頸部郭清組織と一塊として切除することもある。T1N1~3、 earlyT2N1~3 症例もpull-through 法にて原発巣組織と頸部郭清組織を一塊として切除する。lateT2N1~3、 T3、 T4N1~3 症例は舌部分切除、舌半側切除、舌亜全摘出、さらに癌浸潤の程度により下顎骨など周囲組織の合併切除などの原発巣切除と頸部郭清を同時に行う。
表4-1 舌癌の切除方法
| 舌部分切除 partial glossectomy |
舌可動部の一部の切除、あるいは半側に満たない切除をいう(図4-1a)。 | |
|---|---|---|
| 舌可動部半側切除 hemiglossectomy (oral tongue) |
舌可動部のみの半側切除すなわち舌中隔までの切除をいう(図4-1b、図4-2)。 | |
| 舌可動部(亜)全摘出 subtotal-total glossectomy (oral tongue) |
舌可動部の半側を超えた切除(亜全摘出)、あるいは全部の切除をいう(図4-3)。 | |
| 舌半側切除 hemiglossectomy |
舌根部を含めた半側切除をいう(図4-4)。 | |
| 舌(亜)全摘出 subtotal-total glossectomy |
舌根部を含めた半側以上の切除(亜全摘出)、あるいは全部の切 除をいう(図4-5)。 |
|
図4-1 舌部分切除(a)、舌可動部半側切除(b)
図4-2 舌可動部半側切除+口底部分切除
図4-3 舌可動部(亜)全摘出
図4-4 舌半側切除
図4-5 舌(亜)全摘出
舌半側切除+pull-through operation
舌半側切除+口底切除+下顎辺縁切除
舌半側切除+口底切除+下顎区域切除
図4-7 舌癌の外科療法のアルゴリズム
口底癌は正中型(前歯部相当)と側方型(臼歯部相当)に分けられ、多くは正中型である。側方に進展すると、口底粘膜下が疎性結合組織であるため深部に浸潤しやすいことが特徴である。内方に進展すると舌下面、外方に進展すると下顎歯肉・歯槽部や下顎骨に浸潤をきたす。深部に進展するとオトガイ舌筋、舌骨舌筋、顎舌骨筋への浸潤をきたす。また、内舌筋(下縦舌筋、横舌筋、垂直舌筋など)への浸潤をきたしたり、舌根(中咽頭)へ進展する。顎下腺管周囲への浸潤や、舌深動脈、舌下動脈、舌神経、舌下神経周囲への浸潤を示す。頸部リンパ節転移は両側に起こりやすい。
口底癌のT1N0,earlyT2N0 症例は口底部分切除(口内法)を行う。lateT2,T3,T4 症例は原発巣切除(口底全切除)と頸部郭清を同時に行う場合がある。また、舌や下顎骨に浸潤したものでは、舌や下顎骨の合併切除を行う。
頬粘膜癌の亜部位は①上・下唇粘膜部、②頬粘膜部、③臼後部、④上・下頬歯槽溝に分類される。頬粘膜癌の外方進展は頬筋、皮下および皮膚浸潤である。内方進展は上・下顎歯肉や骨に浸潤し、前方進展は口角に、臼後部からの後方進展は粘膜下に沿って下顎骨・翼突下顎隙への浸潤をきたす。同様に、上方進展は上顎結節や翼口蓋窩へ至り、内方進展は軟口蓋、舌根への浸潤をきたす。
T1, T2 症例では頬粘膜切除あるいは放射線治療が行われる。進展例では頬粘膜切除、下顎合併切除、上顎合併切除、皮膚切除、あるいは臼後三角部より上・後方の拡大切除が行われる。
下顎歯肉癌は早期に下顎骨に浸潤し、骨破壊を呈する。特に下顎骨内に深く浸潤した場合は放射線治療での治癒が期待できず、高線量では放射線性骨壊死といった副作用が発生しやすい。また、抗腫瘍薬の骨への移行が悪いことから、外科的切除が基本となる。下顎骨内に進展した腫瘍は直接触知できないために、手術範囲の設定において各種X 線写真やCT、MRなどの画像診断により、骨吸収の深達度、骨吸収型、周囲軟組織への進展状況を正確に把握し、治療計画が立案される。
a.下顎歯肉癌の切除方法(表4-2,図4-8)
下顎歯肉癌の外科療法は原則的に下顎骨切除であり、切除範囲によって基本術式は表4-2のように分類される。その適応は腫瘍の進展範囲によって決定される。
表4-2 下顎歯肉癌の切除方法
| 歯肉切除 gingivectomy |
歯肉粘膜・骨膜のみの切除で骨切除を行わない。 | |
|---|---|---|
| 下顎辺縁切除 marginal mandibulectomy |
下顎骨の辺縁(通常下顎骨下縁)を保存し,下顎骨体を離断しない部分切除。 | |
| 下顎区域切除 segmental mandibulectomy |
下顎骨の一部を歯槽部から下縁まで連続的に切除し,下顎体が部分的に欠損する切除。 | |
| 下顎半側切除 hemi-mandibulectomy |
一側の関節突起を含めた(顎関節離断)下顎骨の半側切除。 | |
| 下顎亜全摘出 subtotal mandibulectomy (with/without condylectomy) |
下顎骨の半側を越える切除で,通常,下顎枝から対側下顎枝の範囲以上の切除。これに関節突起が温存されたか否かを追記する。 | |
| 下顎全摘出 total mandibulectomy |
両側の関節突起を含めて下顎骨を摘出する切除。 | |
図4-8 切除範囲の模式図
b.切除範囲の選択基準
(1)腫瘍の軟組織への進展
原発巣再発が切除後の骨断端よりも軟組織断端から起こっている報告が多く、特に顎舌骨筋や咽頭側へ進展した症例では、辺縁切除では軟組織の切除が不十分となる可能性がある。したがって、下顎骨周囲の深部軟組織への進展症例に対しては、周囲軟組織を含めた区域切除が妥当と考えられる。
(2)骨吸収の深達度
下顎管に達した腫瘍は、下歯槽神経血管束に沿って進展していくため、オトガイ孔、下顎管を含めた区域切除が必要である。X線学的に下顎管に至らない症例の辺縁切除か区域切除かの適応においては、下顎管および骨髄腔内への組織学的浸潤が問題とされる。X線学的に骨吸収が認められた下顎骨の手術標本の組織学的検索では、X線像で骨吸収を認める部位から1cm離れた部位には腫瘍を認めないことから、骨吸収部位から最低1cmの安全域をとる必要性が報告されている。
(3)骨吸収型
X線学的な骨吸収型(平滑型、虫喰い型、中間型)は予後因子とされていることから、これらの吸収様式は骨吸収の深達度と関連して考慮すべきである。X線学的に平滑型では、組織学的な骨浸潤範囲とX線学的な浸潤範囲が一致するが、虫喰い型では、X線の骨吸収像から腫瘍の組織学的骨浸潤を予測することは難しく、切除範囲を大きく設定する必要性がある。また、中間型は、平滑型と虫喰い型との中間的な病態として考慮される。歯槽骨内に限局した症例では辺縁切除を選択すべきであるが、歯槽骨の一部に限局した場合を除けば、虫喰い型の骨吸収像を示す場合や、平滑型であっても下顎管に近接あるいは達する骨吸収を示す症例では、区域切除が妥当と考えられる。
(4)下顎骨の垂直的高さ
辺縁切除では下顎下縁から1cm以下になると骨折の可能性があることが指摘されており、無歯顎萎縮骨の場合では垂直的高さの点で区域切除が選択される場合が多い。
1)歯肉切除はT1,T2に限定され、病理組織学的に歯肉粘膜に限局していることの確認が必要である。
2)T4における骨吸収の深達度は下顎管分類に従い、腫瘍による骨吸収が下顎管の深さに及ぶものとする。
3)骨吸収様式の中間型は、平滑型と虫食い型との中間的な病態として考慮する。
4)切除後の骨欠損については、顎骨の即時あるいは二次再建を必要に応じて考慮する。
5)半側切除、下顎(亜)全摘の対応は、がんの進展により判断される。
図4-9 下顎歯肉癌の外科両方のアルゴリズム
上顎歯肉癌は、下顎歯肉癌と比較して発生頻度は低く、硬口蓋癌はさらにその頻度は低いとされる。上顎歯肉癌(硬口蓋癌を含む)は、下顎歯肉癌と同様に、速やかに骨への浸潤をきたしやすい。解剖学的な特徴として、上方へは上顎洞、鼻腔などへの進展があり、後方では翼状突起、翼口蓋窩、側方では頬粘膜に進展する。硬口蓋癌では軟口蓋へ進展することから、切除による口腔機能への影響が大きい。また、他の口腔癌と異なり、原発巣と頸部リンパ節転移巣の一塊切除ができないという解剖学的特徴を有しているが、頸部リンパ節転移の頻度は下顎歯肉癌より低いとされる。進行癌では、整容的障害の点からも外科療法単独ではなく、放射線療法や超選択的動注などの化学療法を併用した集学的治療が用いられることが多い。切除範囲の決定には、解剖学的に複雑な構造をしているために、画像診断による顎骨への浸潤、鼻腔、上顎洞、翼口蓋窩など周囲組織への進展範囲の精査が重要である。また上顎と下顎では骨質の差異がX線所見に影響するとの意見もある。外科的治療では、外向性の早期癌に対して骨膜を含めた歯肉切除がなされる場合もあるが、多くは上顎部分切除や上顎亜全摘出が行われる。切除によって、上顎洞や鼻腔が交通する場合が多い。上顎洞内に大きく進行した場合には、上顎洞癌に準じた上顎全摘出や拡大上顎全摘出が適応となる(表4-3)。欠損部に対しては整容的障害ならびに言語、摂食障害の点から、顎補綴や遊離組織移植による再建が行われる。
表4-3 上顎歯肉癌の切除方法4)6)
| 歯肉切除 gingivectomy |
歯肉粘膜・骨膜のみの切除で骨切除を行わない。 | |
|---|---|---|
| 上顎部分切除 partial maxillectomy |
上顎歯肉部、上顎洞内の一部、上顎洞正中側、固有鼻腔の一部など、上顎骨の一部を切除する。 | |
| 上顎亜全摘出 subtotal maxillectomy |
眼窩底のみを温存し上顎骨を切除する。 | |
| 上顎全摘出 total maxillectomy |
上顎骨のすべてをその周囲組織を含めて切除する。 | |
| 上顎拡大全摘出 extended maxillectomy |
上顎骨とともに、眼窩内容や頭蓋底を切除する。 | |
口腔癌の外科手術に際し気管切開がしばしば行われるが、その適応については各施設で異なっているのが現状である。一般的には舌原発巣の切除範囲が広い場合(可動部半側切除を越える場合)、下顎骨の半側以上の切除を行った場合、両側の頸部郭清を行った場合および再建皮弁のボリュームなどで気道閉塞の可能性がある場合などに気管切開が行われることが多い。
口腔癌の頸部リンパ節転移の制御は予後を左右する重要な因子である。頸部リンパ節転移に対する治療は手術療法(頸部郭清術)、放射線療法、化学療法、あるいはこれらの併用療法があるが、この中でも頸部郭清術は最も重要な位置を占めている。しかし、その術式の選択は施設により異なっているのが現状である。
頸部リンパ節はその部位により、Level Ⅰ~Ⅳに分類される。さらにLevel Ⅰ,ⅡおよびⅤはA,B に分けられている(図5-1)。一般的に口腔癌の所属リンパ節は Level Ⅰ~Ⅴとされている。
Level Ⅰ:オトガイ下リンパ節(Level ⅠA)、顎下リンパ節(Level ⅠB)
Level Ⅱ:上内頸静脈リンパ節(Level ⅡA:副神経より前方、Level ⅡB:副神経より頭側)
Level Ⅲ:中内頸静脈リンパ節
Level Ⅳ:下内頸静脈リンパ節
Level Ⅴ:副神経リンパ節(Level ⅤA),頸横リンパ節、鎖骨上窩リンパ節(Level ⅤB)
Level Ⅵ:前頸部リンパ節
図5-1 頸部リンパ節のレベル分類(Level Ⅵは省略)
従来、頸部郭清は内頸静脈、胸鎖乳突筋、副神経を切除する根治的頸部郭清術(RND)が行われてきたが、術後の機能障害が大きい。そこで、RNDの根治性を損なうことなく、より低侵襲の手術術式が検討され、根治的頸部郭清術変法(MRND)が行われるようになった。さらに原発部位とレベル別のリンパ節転移頻度が検討され、口腔癌ではLevel Ⅰ~Ⅲの転移頻度が高いことが示された。そのため、治療的頸部郭清術の一部や予防的頸部郭清術においては、肩甲舌骨筋上頸部郭清術(SOHND)のような選択的(部分的)頸部郭清術が行われるようになっている。
表5-1 口腔癌における頸部郭清術の分類
| (1) | 根治的頸部郭清術(radical neck dissection:RND) Level Ⅰ~Ⅴのリンパ節・組織を胸鎖乳突筋、内頸静脈、副神経を含めて郭清する。 |
|
|---|---|---|
| (2) | 根治的頸部郭清術変法(modified radical neck dissection:MRND) Level Ⅰ~Ⅴのリンパ節・組織を郭清するが、胸鎖乳突筋(M)、内頸静脈(V)、副神経(N)のいずれか1つは保存する。保存的頸部郭清術(conservative neck dissection)あるいは機能的頸部郭清術(functional neck dissection)とも表現される。保存した組織によりtype Ⅰ~Ⅲに細分類される。 type Ⅰ:副神経を保存する。 type Ⅱ:内頸静脈と副神経を保存する。 type Ⅲ:胸鎖乳突筋、内頸静脈、副神経のいずれも保存する。 |
|
| (3) | 選択的(部分的)頸部郭清術(selective neck dissection:SND) 頸部リンパ節の3つあるいは4つのレベルを選択的に郭清する。口腔癌ではLevel Ⅰ~Ⅲが選択されることが多いが、郭清範囲により下記のような術式がある。 (i)肩甲舌骨筋上頸部郭清術(supraomohyoid neck dissection:SOHND) Level Ⅰ~Ⅲのリンパ節・組織を郭清する。 (ii)拡大肩甲舌骨筋上頸部郭清術(extended supraomohyoid neck dissection:extended SOHND) Level Ⅰ~Ⅳのリンパ節・組織を郭清する。 |
|
| (4) | 超選択的頸部郭清術(superselective neck dissection:SSND) 頸部リンパ節の1つあるいは2つのレベルを選択的に郭清する。 (i)舌骨上頸部郭清術(suprahyoid neck dissection:SHND) Level Ⅰ,Ⅱのリンパ節・組織を郭清する。 (ii)顎下部郭清術(submandibular neck dissection:SMND) Level Ⅰのリンパ節・組織を郭清する。 |
|
| (5) | 拡大頸部郭清術(extended neck dissection) Level Ⅰ~Ⅴ以外のリンパ節・非リンパ組織を切除する。 |
|
口腔癌のN0 症例に対する予防的頸部郭清術については、後発頸部リンパ節転移例の予後が悪いという意見や、予防的頸部郭清術に用いられるSOHNDは機能障害が少なく、また病理学的病期の決定が可能で、術後の治療方針の立案に有用であるという理由から、これを推奨する意見がある。一方、予防的頸部郭清を行った場合と後発リンパ節転移に対して救済治療を行った場合で頸部制御率に差がないことから、厳重な経過観察を行い転移が明らかになった時点で頸部郭清を行う“wait and see”がよいとする意見もあり、統一した見解はない。しかし、原発巣切除や原発巣切除後の再建手術のために手術野が頸部に及ぶ症例では、予防的頸部郭清が行われる。
舌癌ではT1N0 やearlyT2N0 症例に対して通常は経過観察が行われる。しかし、T1やearlyT2症例でも潜在性転移が強く疑われる場合や、潜在性転移率の高いlateT2以上の症例に対しては予防的頸部郭清が行われる。また、原発巣が口底部にまで及ぶ症例や再建手術を必要とする症例に対しても予防的頸部郭清が行われる。その術式としては、口腔癌はLevel Ⅰ~Ⅲに転移する頻度が高いことから、SOHNDが選択される。最近では、飛び石転移によるLevel Ⅳへの転移も約16%認められることから、Level Ⅳを含めたextended SOHNDを推奨する意見もある。一方で、口腔癌ではLevel ⅡBへの頸部リンパ節転移が6%と非常に低いことが報告されたが、Level ⅡBの郭清の省略については議論の余地がある。T3症例に対してもSOHNDが推奨されているが、RND/MRNDを推奨する意見もある。また、T4症例においてもMRNDを推奨する意見がある。潜在性頸部リンパ節転移に関しては、T2症例であっても4~5 mm以上の浸潤深度を示す舌癌では潜在性転移が高いことや、E-cadherinの減弱や浸潤能の評価など潜在性リンパ節転移予測因子の研究が進んでいることから、これらを参考にする必要がある。
最近では口腔癌の潜在性リンパ節転移の診断におけるセンチネルリンパ節生検の有用性に関する検討がなされている。
N1~3症例に対する治療的頸部郭清ではRND/MRNDを基本とするが、MRNDは温存する臓器と癒着(被膜外浸潤)を認めないなど転移の状況を考慮する。また、Level ⅠのN1 症例ではSOHNDが選択される場合もある。
【補足】センチネルリンパ節生検
口腔癌のT1, 2N0 症例の潜在性リンパ節転移に対して、精度の高い診断法としてセンチネルリンパ節生検について検討がなされ、その有用性に関する報告が増加している。センチネルリンパ節の同定法では色素法、放射線同位元素法、CT Lymphographyを用いた方法などが検討され、概ね100%に近い同定がなされている。また、得られたセンチネルリンパ節の潜在性転移の検出法として、免疫組織学的評価法ならびに分子生物学的手法が検討され、さらに分子マーカーについては精度ならびに簡便性の両面から検討がなされている。欧州ではすでにガイドラインが作成されている。
リンパ節被膜外浸潤例、多発性リンパ節転移例などでは、頸部再発や遠隔転移をきたしやすく予後不良例が多いことから35)、頸部郭清後に放射線療法、化学放射線療法が行われる。また遠隔転移を予防するために補助化学療法が行われることもある。
頸部リンパ節転移に対しては原則として手術療法が行われるが、手術適応のない症例に対しては、放射線療法、化学放射線療法が行われる。
遠隔転移のない進行例においては、治療効果を高める目的から、術前または術後に化学療法あるいは放射線療法、またはそれらの併用が補助療法として行われている。
術前補助療法の目的は、手術の根治性を高め、潜在性微小転移を根絶することによって、生存率の改善を図ることである。また、腫瘍の縮小により口腔の機能温存を期待する。
a.化学療法
頭頸部癌は、抗腫瘍薬に対する感受性が高いこと、根治的治療前は全身状態が良いこと、原発巣・頸部の血管系が傷害されていないことなどから、高い殺細胞効果が期待できる。しかし、根治的治療後の遠隔転移率の低下はみられるものの、生存率の改善への寄与を示すエビデンスは乏しい。最近の口腔癌のみを対象としたランダム化比較試験では、術前化学療法によって、下顎骨合併切除や術後放射線治療の回避などの恩恵があることが示唆されている。標準的な化学療法としては、CDDP + 5-FU(PF 療法)が主なレジメンであるが、最近はDTXを加えたTPF療法が増えている。
b.放射線療法
原発巣・頸部に対する術前補助療法として放射線療法が用いられる。近年、進行頭頸部癌において、加速過分割照射法の原発巣・頸部制御率が標準照射法と比較して良好なことが示され、これを背景に術前にも加速過分割照射を適用する試みがなされている。しかし、原発巣・頸部制御率ならびに生存率の改善への寄与に関しては、さらなる研究成果が待たれる。
c.化学放射線療法
抗腫瘍薬を併用することで、放射線の治療効果を増強し、さらに潜在性転移を制御することを目的とする。併用方法には、同時併用、継続併用、交替療法があるが、同時併用療法が最も効果が高いことが報告されている。 近年は原発巣・頸部制御率および生存率の改善、あるいは縮小手術の適用を目的として、外科療法の術前補助療法として用いられ、その有用性が報告されているが、ランダム化比較試験はなされていないため今後の結果が待たれる。
術後補助療法の目的は術後の再発を予防するとともに、潜在性転移を根絶し、生存率の改善を図ることである。主に術後の再発高危険症例、すなわち切除断端陽性例や多発リンパ節転移例、被膜外浸潤を有する症例に対して施行される。近年、極めて高い原発巣・頸部制御効果が示されている化学放射線療法を補助療法として用い、原発巣・頸部制御率および生存率の改善が期待されている。
a.化学療法
術後化学療法は根治的手術の原発巣・頸部制御ばかりではなく、遠隔転移の制御を目的として用いられる。しかしながら、進行頭頸部癌を対象としたランダム化比較試験からは、遠隔転移率の低下は認められるものの、生存率の改善への寄与を示すエビデンスは得られていない。
b.放射線療法
術後放射線療法は原発巣・頸部制御率の改善を目的に施行されているが、制御率は35~70%で効果には差がある。切除断端陰性症例における微小な残存癌細胞の根絶には50Gyが必要で、断端陽性などの術後再発高危険症例においては、より高線量の放射線が必要なことが示されている。しかし、63Gy以上の線量増加は原発巣・頸部制御率の改善に寄与しないことも示されている。また、加速分割照射法も術後放射線療法として試みられているが、ランダム化比較試験でも結果は一定ではない。
c.化学放射線療法
進行頭頸部癌に対する術後補助化学療法の効果は、遠隔転移率の低下への寄与は認められたものの、生存率の改善には至っていない。術後照射群と化学放射線群(継続併用)の大規模ランダム化比較試験でも、化学放射線群では遠隔転移率の低下がみられたものの、生存率の改善には至っていない。しかし、サブグループ解析において、術後再発高危険症例(多発リンパ節転移、被膜外浸潤、切除断端陽性、脈管および神経浸潤)では、化学療法の併用により原発巣・頸部制御率および生存率の改善があったとされている。その後の大規模ランダム化比較試験によって、術後再発高危険症例における化学放射線療法の原発巣・頸部制御率および生存率の改善への寄与が示されている。
以上のように、術後再発高危険症例に対し、化学放射線療法は標準的治療とされるが、有害事象の発生頻度や程度が高いことを考慮する必要がある。
口腔癌の根治的治療後の原発巣および頸部での再発は、最も大きな予後不良因子であることは言うまでもない。各種根治的治療後の原発巣・頸部再発率は通常24~48%と報告され、そのうち原発巣再発が半数以上を占めている。また、再発癌の75%以上は一次治療後2年以内に認められており、これらを考慮した経過観察が必要である。
再発癌の治療法としては、外科療法、放射線療法、化学療法、また最近では、分子標的治療薬を用いた治療や、癌特異的ペプチドや樹状細胞を用いた免疫療法なども試みられている。また、姑息的な放射線療法や化学療法を含む緩和治療が挙げられる。これらは、再発部位や再発時の進行度および一次治療内容、患者の全身状態によって選択されている。
再発癌が切除可能と判断でき、患者の全身状態も良好であれば、通常はまず外科療法が選択される。特に放射線療法の既往がある症例においては、外科療法は第一選択であり、化学療法や放射線療法、化学放射線療法に比べ予後が良いことが報告されている。しかし、再発時に進行しているものや進行癌の再発例においては、一般的に予後不良である。また、原発巣と再発部位にも影響し、外科療法により最も予後が良好であるのは、頭頸部癌においては、喉頭癌での原発巣再発である。一方、咽頭癌の原発巣再発は一般的に不良で、口腔癌における原発巣再発はその中間であり、最も不良であるのは頸部再発であることが報告されている。口腔癌を含む頭頸部再発癌における外科療法の治療成績は15~67%とされ幅が広いが、最近では、2年無病生存率で44%、また、メタ・アナリシスでは、5年生存率39%と報告されている。
再発癌が切除不可能な場合や患者の全身状態により手術不能である場合、また再発癌手術後の補助療法として、放射線療法や化学放射線療法が選択されている。再発癌に対しては通常50~60 Gy以上の高線量の外部照射が選択される場合が多い。
既治療として根治線量(60~70Gy)の照射が施行された原発巣再発癌に対しては、再照射は困難で、また、切除不可能である場合は、必然的に化学療法が選択されることになる。化学療法は通常CDDPやCBDCAなどの白金製剤、5-FUやS-1、PTXやDTXといったタキサン系をベースにした多剤併用療法が施行される場合が多く、単剤に比べて奏効率は高いものの、生存率を改善するまでには至っていない。
再発癌や切除不能な進行癌では放射線療法や化学療法に対し抵抗性をもつものが多く、それらに対する全く新しい治療法の開発が望まれている。その主なものとしては分子標的治療や遺伝子治療であり、現在phase Ⅰ,Ⅱ,Ⅲの臨床試験が頭頸部進行再発癌、転移性癌に対し行われている。
分子標的治療薬としては、MMPおよびNF-κBの阻害薬、VEGF、VEGFR、およびEGFRなどを分子標的とした治療薬があり、単独または化学療法や放射線療法との併用による効果が報告されているが、生存期間および生存率の改善までには至っていない。ただcetuximabはphase ⅡあるいはⅢの臨床試験で化学療法および放射線療法に対する上乗せ効果があり、生存期間の改善を示す報告がある。
遺伝子治療は、増殖型アデノウイルスベクターを用いた頭頸部再発癌に対するphase Ⅱの臨床試験が行われ、14%の症例に腫瘍縮小効果を認めたという報告があるが、症例数が少なく評価するにはいまだ十分ではない。
口腔癌の切除不能な再発症例や進行症例に対しては、癌特異的ペプチドや樹状細胞を用いた癌ワクチン療法が試みられており、phaseⅠの臨床試験も行われている。ペプチドにはsurvivin-2B,URLC10,TTK,WT1が用いられており、特にsurvivin-2Bを用いた場合には、一部の症例でPRや腫瘍マーカーの低下といった臨床効果がみられており、少なくとも多くの症例で特異的細胞傷害性T細胞の誘導が確認されている。現状ではいずれの臨床成果も十分とはいえないが、有害事象が少ないことなどもあり、今後標準的治療としての役割が期待される。
口腔癌を含むがん治療では、受診時の不安や告知後の抑うつに対する対応、術後や化学放射線療法施行時・後の疼痛管理やせん妄を含む精神症状のケアが必要となることが多く、早い段階から緩和医療を開始する必要がある。さらに、がんの終末期では、がん性疼痛、呼吸器症状、消化器症状、精神症状、出血などが生じるが、口腔癌ではそれ以外に気道狭窄による呼吸困難、嚥下障害による栄養障害、構音障害によるコミュニケーション障害、整容的な障害などを生じることがある。しかし、疼痛管理、呼吸器症状・消化器症状・精神症状の緩和を除いて、患者や家族のQOLの向上を図る系統的な支持療法は確立されておらず、経験や知識に基づいた個々の対応に委ねられてきた。近年、患者の意思を尊重した終末期医療のあり方が再検討され、支持療法の確立を目指した取り組みも必要である。
口腔癌を含むがん性疼痛の制御は、終末期だけではなく治療中を含め早い段階から必要になることも多い。
基本的には、がん性疼痛の制御はWHOの提唱する3段階の薬物療法を中心に行われており、「がんの痛みからの解放」第2版が1996年にWHOから出版された。がん性疼痛の治療は、第一に「痛みに妨げられない夜間の睡眠」、第二に「安静時の痛みの消失」、第三には「体動時の痛みの消失」を目標としている。
しかし、骨転移などの体動時痛など疼痛制御が困難な場合もあり、患者および家族に対する適切な説明が必要となる。
WHO方式がん性疼痛治療法は、「鎮痛薬使用の5原則」および「三段階除痛ラダー」から構成されている。鎮痛薬使用の5原則は、(1)経口的、(2)時間を決めて規則正しく、(3)除痛ラダーにそって効力の順に、(4)患者ごとの個別的な量で、(5)その上で細かい配置を、の5点にしたがって鎮痛薬を使用するというものである。三段階除痛ラダーは、痛みの強さによる鎮痛薬の選択ならびに鎮痛薬の段階的使用法を示している。WHO方式がん性疼痛治療法は、非オピオイド鎮痛薬およびオピオイド鎮痛薬の使用に加え、抗うつ薬や抗痙攣薬を含めた鎮痛補助薬の使用や副作用対策、心理社会的背景などを包括的に用いた除痛法である。がん治療(手術、放射線治療、化学療法など)や神経ブロックなどにより痛みの原因が除去されたり減少した場合には、鎮痛薬の漸減が必要となる。
実際のがん性疼痛制御に関しては、様々な薬剤の使用および精神的な対応を含め緩和ケアチームや緩和ケア科および精神腫瘍科との密接な連携が必要となる。
出血は、原発部位および頸部転移巣の皮膚浸潤部や動静脈からの出血として認められる。大量出血はショックや気道閉塞により死に直結し、また慢性持続性の出血は貧血をきたし、QOLの低下を招く。
腫瘍浸潤による出血を生じた場合は、用手的な圧迫や局所止血剤の貼付が有効であるが、腫瘍の栄養血管である外頸動脈の結紮や、IVR(Interventional Radiology)を応用して白金コイルやゼラチンスポンジ等を塞栓物質として用い、動脈塞栓術を要することもある。
進行癌患者における栄養療法の目標は、症状緩和および快適性にある。終末期においても、摂食機能から導かれる口腔感覚や食べる喜びを維持することが望ましいが、口腔癌の存在や治療の影響により経口摂取が困難なことが多い。口腔癌患者では、咽頭より下部の消化器に異常を認めないことが多いため、経口摂取が困難な場合は経腸的な栄養摂取が好ましい。そのため、経口摂取が困難となることが予想される場合は、全身状況が悪化する前に経皮内視鏡的胃瘻造設(PEG)を行い、栄養摂取および薬剤投与のための経路を確保することが望ましい。
a.癌に随伴する症状
口腔癌治療においては、口腔のみならず、転移巣や治療による副作用が認められる臓器をも含めた全身的な管理が必要となる。悪液質や癌随伴症候群への対応も必要である。口腔癌でよくみられる高Ca血症は、腫瘍による骨破壊もしくは副甲状腺ホルモン関連タンパクの異常産生によって引き起こされ、悪心・嘔吐、全身倦怠感、意識障害を生じる。
高Ca血症の治療としては、生理食塩水による大量輸液を行い脱水を回避しながらCaの排泄を図るが、急激または重度な高Ca血症では、ヒドロコルチゾンやカルシトニン、ビスフォスフォネート製剤を使用する。がん患者での低Na血症は、低栄養によるNa摂取不足および腫瘍による抗利尿ホルモンの異常産生などにより発症する。治療としては、NaClを用い緩徐に経静脈的な補正を行う。骨転移による疼痛に関しては、放射線外部照射や放射性ストロンチウム(89Sr)の投与、ビスフォスフォネート製剤、抗RANKL抗体が有効なことがある。
b.上気道閉塞
腫瘍や周囲組織の浮腫、治療後の気道の狭窄、あるいは出血、肺炎、気道分泌物の増加により呼吸困難を生じる際には、慎重な気道管理が必要である。原因や気道狭窄部位とその程度により対応を選択する。上気道閉塞の症状は咳から始まり、冷汗・頻呼吸・陥没呼吸・吸気時の高調喘鳴・チアノーゼを認める。呼吸苦への対応としては、体位や呼吸法の工夫、去痰法、酸素療法などがあり、また精神的ケアによる不安の軽減も必要である。浮腫に対してはステロイドの投与が有効な場合がある。気道異物により気道が閉塞している場合は、速やかに用手的に掻き出すか、ハイムリッヒ手技や腹部突き上げによる異物の除去を試みる。咽頭ならびに喉頭の浮腫や腫瘍浸潤、外方からの腫瘍による圧迫が原因で気道が閉塞し、重篤な状況やそれが予見される場合は、気管内挿管が可能か判断する。高度の気道浮腫や狭窄・閉塞などの気管内挿管が困難な場合は、気管切開を考慮する。気管切開を行うに際しては、生命予後と患者個々のQOLを考慮し、その適否を決める必要がある。なお気管切開の際には、腫瘍による気管の偏位に配慮する必要がある。
約半数のがん患者が何らかの精神症状を有し、なかでも適応障害、うつ病とせん妄の頻度が高い。終末期で入院を要する患者ではせん妄の割合が増加し、30~90%に及ぶことが示されている。がん患者の適応障害やうつ病の危険因子として、若年者、独居、進行がん・再発がん、痛みの存在、身体的機能の低下、うつ病の既往、神経質な性格傾向、周囲からの乏しい援助などが知られている。これらの中でもコントロールできない痛みの存在は不安や抑うつの最大の原因の一つであり、精神症状とがん性疼痛が同時に存在する場合には原則として除痛が優先される。せん妄は、軽度から中程度の意識混濁に、幻覚、妄想、興奮などの様々な精神症状を伴う特殊な意識障害であり、がんに関連して発現してくるストレス疾患として、適応障害やうつ病などとは異なる精神症状である。
a.適応障害への対応
医療者との良好な信頼関係を基礎とした支持的コミュニケーションが不可欠であり、効果が不十分な場合は薬物療法として半減期の短い抗不安薬を投与し対応する。
b.うつ病への対応
支持的コミュニケーションに加えて,薬物療法として抗うつ薬を投与する。
c.せん妄への対応
原因となる薬剤,脱水,高Ca 血症,感染の除去を試み,薬物療法として抗精神病薬を併用することが多い。

医師 頭頸部外科部長
菅澤 正 (すがさわ まさし)
SUGASAWA Masashi
日本耳鼻咽喉科学会専門医・指導医、 日本頭頸部外科学会頭頸部がん専門医・指導医、 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会専門医・指導医、 日本気管食道学会認定気管食道科専門医、 日本がん治療認定医機構がん治療認定医、 緩和ケア基礎研修会修了、 臨床研修指導医講習会修了、 医学博士
医師の詳細はこちら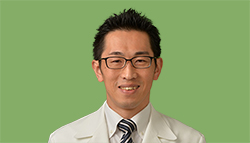
医師 耳鼻咽喉科部長
明石 健 (あかし けん)
AKASHI Ken
日本耳鼻咽喉科学会専門医・指導医、 日本頭頸部外科学会 頭頚部がん専門医・指導医、 日本がん治療医認定機構 がん治療認定医
医師の詳細はこちら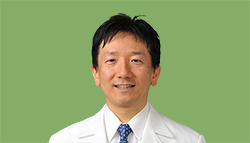
医師 腫瘍内科 部長
大山 優 (おおやま ゆう)
OYAMA Yu
日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、 米国腫瘍内科専門医、 米国血液科専門医、 日本臨床腫瘍学会指導医、 日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医、 日本臨床腫瘍学会協議員、 日本臨床肉腫学会理事、 日本サルコーマ治療研究学会評議員
医師の詳細はこちら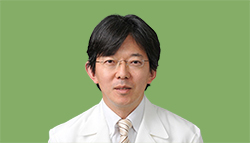
医師 放射線科 部長・放射線治療センター長
庄司 一寅 (しょうじ かずふさ)
SHOJI Kazufusa
日本放射線腫瘍学会・日本医学放射線学会 放射線治療専門医、 厚生労働省指定オンライン診療研修修了
医師の詳細はこちら口腔がんの治療には、主に手術、放射線療法、化学療法などがあります。がんの生じた場所や進行度などによって最適な治療法は異なります。口腔がんは舌や歯肉、頬などに生じるため、食事や会話などの機能と大きく関わり、治療後に嚥下障害(のみこみづらい、むせてしまう)、構音障害(うまく言葉が発音できない)などの機能障害が治療後に起こることがあります。治療法を選ぶ際は、病気を治すことだけでなく、その後の生活のことまで考え、納得できる治療法を選ぶことが大切です。
舌は味を感じるだけでなく、食物をのどに送り込む働きがあります。そのため、舌が大きく切除された場合は食物がうまく飲み込めず、スプーンを使ってのどの奧に食物を流し込んだり、水分にトロミをつけて誤嚥を予防したりするなどの工夫が必要となることがあります。がんの場所や手術方法などにより注意点はそれぞれ異なりますので、手術後に嚥下リハビリを行い、具体的な注意点を身につけてから退院します。
治療が成功してもその後に再発したり、転移が見つかったりことがあるため、一般的には最低5年は通院した方が望ましいといわれています。また、口腔がんは前述の通り様々な機能障害が起こりえますが、特に誤嚥は命に関わることもあるため、食事の際には誤嚥を防ぐような工夫が必要です。具体的な注意点は人それぞれ異なるため、治療後の入院期間中に、主治医や看護師、ST(言語聴覚士)などによく相談しておくと安心です。